こんにちは!現役京大生のぽとろです!
突然ですが皆さんは「逆転“不”合格」についてご存じでしょうか?端的に言えば「良い判定が出ていた人が本番で何かしら失敗したり、本番までの間に準備を怠ったりして不合格となってしまう」という現象のことです。
私は多浪の末に京都大学に合格したわけですが、その間に4度の「逆転不合格」を喫したことがあります(詳しくは後述)。
今回は私のような失敗をする受験生が少しでも減ったらいいなと思い、このような記事を書きました。
興味のある所だけでも読んでいただければ幸いです。
私の「逆転不合格」歴
まずは私の逆転不合格の経歴について書きましょう。
私は国公立前期試験で2度、後期試験で2度の逆転不合格を経験したことがあります。いずれもA判定を取っていたのに落ちました。
前期試験は過去問演習でも合格ラインを超える点数を取れていました。
後期試験は共テの割合が高い方式でしたが、共テ後の各予備校のリサーチ結果でもA判定が出ていました。
先に言っておきますが、緊張で問題が解けなかったとか風邪で体調を崩していたとかいうわけではないのです。単純に自分の詰めの甘さや能力不足で落ちたのです。
それではなぜ私がこのような大失態を4度も犯してしまったのかについて、解説していきましょう。
ちなみに以下はほとんど私の経験に基づいたものですが、「逆転不合格をする人ってこういう特徴があるよね」という一般論も混ぜています。
是非自分に当てはまっていないか確認しながら読んでください。
逆転不合格をする人の特徴
それでは逆転不合格をする人の特徴を解説していきます。
とはいったものの、大半の逆転不合格erは1つ目の理由で逆転不合格を喫しています。
2つ目、3つ目は私の経験則を書いた補足的なものです。
①“自称”数強
逆転不合格の最も多い原因、それは「自称数強」です。
私も国公立前期は2度これのせいで逆転不合格をやらかしました。
「自称数強」とは端的に言えば「本番確実に数学で稼げるほどの学力はないのに数学に依存した得点戦略を立ててしまい、当日数学で失敗して撃沈する」という現象です。
「数学以外でも言えることじゃないか!」というヤジが聞こえてきそうですが、これには理由があります。
受験における数学という科目には、他の科目にはない大きな特徴があります。それは対策が未熟な場合、少しの要因で得点が大幅に減少することがあるということです。
具体的に説明しましょう。
数学は他の科目と違って、一部分が分からなかった時の影響が非常に大きいです。
例えば英語では、一つの単語が分からなくても長文全体が読めないということはほぼ起きません。
ですが数学ではこれが起きうるのです。例えば、どこかで解法が浮かばなかった場合、その問題はその先へ進めなくなります。一問30点の問題で5点分しか記述できなかった場合、いくらその分からない解法以降の部分ができたとしても、25点は絶対に獲得できません。
そして、この「解法が分からずにつまづく」という現象は本番の些細な傾向変化で起こります。
傾向が変わると前年まで通用していた解法や思考法では解けない問題が出題され、その大学の傾向しか対策しなかった人、柔軟な解法を選択するための基礎力が不足している人は太刀打ちできなくなってしまうというわけです。
これが「自称数強」です。①志望校に特化した対策しかしていない②基礎力が不足しているという二つの特徴が自称数強を生みます。
彼らは傾向に合わせた勉強はしているので、模試、特に冠模試(大学別模試)では良い点数が取れることが多いです。
模試の数学で点が取れ、良い判定が出て慢心してしまうのです。これが彼らの敗因です。
私の場合は二度の逆転不合格の際は両方とも数学の傾向変化が起こっていました。
秋の模試やでは十分に点が取れていたため本番も十中八九受かると思っていました。実際は模試はそれまでの過去問を解いて覚えた解法がたまたま出題されていただけで、本番それまでとは異なる傾向の問題やセットが出題され、私の得点の源となっていた解法がことごとく通じず、結局悲惨な点を取ってしまいました。
傾向変化が起こっていなかったら間違いなく受かっていたと思っていますが、そんなことを言っても悪いのは対策を怠った自分自身です。
結局基礎を固め、大学の傾向に偏りすぎない解法暗記が必要だったのです。
ここまで数学の話となってしまいましたが、いくら数学できちんと基礎を固め、傾向に依存しすぎない対策を講じていたとしても、たまたま自分が知らない解法が出題された場合、数学で大きく点数を落とすということは普通に起きます。
ですから、ここで私が強調したいのは、「自称数強からまっとうな数強になれ」ということではなく、「数学の傾向変化で失敗しないための対策をしつつ、数学で多少点が取れなくても受かるくらい他の教科の点数を上げよ」ということです。
私は合格した年、前年からの反省で数学で傾向変化しても点が取れるように対策していましたが、結局本番は大コケはしなかったものの、想定より低い点数しか取れませんでした。しかし、数学の対策と同時に数学が足を引っ張っても受かるように英語、国語、社会を伸ばしていたおかげでなんとか合格することができました。
受験生の皆さん(特に数学に自信がある人)は「自称数強になっていないか」、「数学で取れなくても受かるような他教科の得点戦略を立てられているか」を常に確認していただきたいです。
②学部の定員が少ない
ここからは経験談と補足です。
私は国公立後期試験でも逆転不合格を経験しているのですが、その際落ちた原因は二つあり、「学部の定員が少なかったこと」と「共テ割合が高かったこと」があげられます。
まずはなぜ学部の定員が少ないことが逆転不合格につながるかについてです。
理由は単純で、受験者層の振れ幅が大きいからです。
例えば定員が5人の学部であれば、いつも地方の人しか受けないようなところに突然東大落ちの人が来たらそれだけで定員は実質4人になります。
これは極端な例ですが、その年の傾向によって受験者層が変化することはよくあります。
例えば教育課程が変わるときには浪人を避けるために滑り止めのレベルを下げる人が増えます。結果、普段よりレベルの高い受験生が集まります。
このようなことが起これば、いくら模試で判定が良くてもレベルの高い受験生たちに枠を奪われ不合格となってしまいます。
定員が少ない学部を避ける必要はないですが、多少レベルの高い受験生が集まったとしても受かる実力があるのか、検討してから出願しましょう。
③共テ割合の高い試験
また、共テ割合の高い試験にも注意が必要です。
「共テ割合が高いなら二次試験の不確実要素をできるだけ減らせるから、結果として合格の見込みが見定めやすいのではないか」「共テリサーチ(共テの点により各大学の合格率を判定するもの)でAならほぼ確実に受かるんじゃないか」という意見もあると思います。
共テ割合が高い試験に注意すべき理由は、後期試験の共テリサーチは判定の信頼性が薄いからです。
共テリサーチのA判定の基準は「二次試験でこのくらいの点が取れるはずだ」という想定の下で作られています。
後期試験はデータが少なかったり、前期試験と異なる傾向や難易度で出題されることも多く、二次試験の想定点数は容易に算出できないのです。
また、上述のこととも重なりますが、後期試験では定員が少ない分受験者層の振れ幅が大きく、周りがどれくらい点を取ってくるのかも想定が難しいです。
したがって前期試験と後期試験の共テリサーチは別物と考えなければなりません。
私は共テリサーチでA判定(しかもある程度余裕があった)が出て、なおかつ受ける学部の共テ割合が7割を超えていたことから、ほぼ確実に受かると思って調子に乗っていました。
二次試験の対策をしなかったわけではないのですが、結果として想定よりも必要とされる点数が高く、不合格となってしまいました。
まとめ
大学受験において絶対はありません。逆転不合格は誰の身にも起こりうる現象です。是非受験生の皆さんはこの記事を参考にして、志望校合格の可能性を少しでも高める努力をしていただければと思います。
抜かりなく準備をしてきっちり成功を掴み取ったという経験は先の人生でも必ず役に立ちます。
A判定の皆さんが「順当合格」できることを祈っています。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

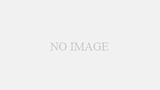
コメント