こんにちは!現役京大生のぽとろです!
今回は記述模試では点が取れるのに共テではなかなか点が伸びないという方に向けて、共テの点数を伸ばす方法について解説していきます!
この記事をご覧の方は「記述模試では良い点が取れているのに共テ形式では全然点が取れない」、「記述模試より共テ模試のほうが判定が悪い」というようなお悩みを抱えていらっしゃるかもしれません。
そんな方に向けて、共通テストで高得点を獲得し京都大学に合格した私の経験から、共通テストの点をしっかり伸ばしていく方法について紹介していきます!
以下では「基礎力」、「問題形式への慣れ」、「素早い情報処理」、「時間戦略」という4つのテーマに着目して解説を進めていきます。興味のあるところだけでもご覧ください。
基礎力
まず大前提として共テで点を伸ばすには基礎的な学力が必要です。「記述模試で点が取れているのだから基礎はもう固まっている」と考えているかたもいらっしゃるかもしれませんが、一度ご自身の基礎力についてもう一度考えてみてください。
重要なのは記述模試では低・中得点勝負、共テは高得点勝負であるということです。記述模試では多くの人が4~6割付近の点数を取るテストなので、仮に一部の分野の基礎が抜けていても他の部分でカバーすることができてしまいます。逆に共テは多くの人が7~9割を取るテストで記述模試に比べて「点は取れて当たり前」という側面が強いため、一分野の失点が大きく影響します。
自分の基礎力が足りているかどうかの見極め方は、共テの得点を分野ごとに調べるという方法があります。仮に一部の分野に失点が偏っていることが分かったらそこは基礎力が足りないと考えて、基本的なところから勉強しなおすことが必要です。
問題形式への慣れ
共テで点を稼ぐには共テ特有の問題形式を熟知し、慣れている必要があります。例えば英語リーディングでは大問ごとにどのようなテーマが扱われているか、どのような事柄を問われるか、どれくらいの長さの文章かなどが大体あらかじめ決まっています(時々変わることもありますが、そこまで大きく変わることはありません)。そのような形式を知っているだけでも頭の使い方や目線の動かし方などの効率が上がります。
問題形式にまだ慣れていないという人は一度過去問や予想問題を見て、どの大問でどのような問題が出ているかを一度自分で整理してみましょう。それだけで対応速度が大きく変わります。
素早い情報処理
共テは時間との戦いですから、情報処理の速度も重要になってきます。これは特に時間設定の厳しい国語、数学、英語リーディングで重要です。
国語や英語リーディングでは素早く本文の内容を掴む技術が、数学では計算能力だけでなく数式を理解する能力や素早く提示された条件を数式に落とし込む技術が必要となってきます。
それらは模試や本番で頑張ってどうにかなるものではないので、自身の処理速度に自身が無い場合は個別で対策をするようにしましょう。その際、「精度を保ったまま速度を上げる」ということを意識することがポイントです。
時間戦略
最後に時間戦略についてです。先述の通り共テは時間がかなり限られた試験なので、事前にどこに何分かけるかという時間戦略を定めておくことが必須となります。
なぜ事前に決めておく必要があるかというと、共テは大半の人が時間内にすべての問題をしっかり考え抜くことができる試験ではないため、試験中に「どこから解こうか」、「もう少しで解けそうだけど次にいくか、もしくは粘るか」などの決断をするわずかな時間さえも惜しいからです。
あらかじめ「解く順番」と「大問ごとの使う時間」を決めておきましょう。
解く順番はもちろん最初からである必要はありません。例えば私の場合、国語の試験は漢文、古文、評論文、小説、実用文の順で解いていました。確実に点が取れる大問から順につぶしていきましょう。
また大問ごとの時間は何があっても守らなければいけません。もう少しで解けそうでも諦めて次に行きましょう。計画通り解き進めていって、時間の余裕が生まれたら最後にその問題にまた戻ってくれば良いのです。粘って解けなかった時のロスは、時間の厳しい共テでは絶対に排除すべきものです。加えて時間が経った後だと案外思いつかなかったことに気づけることもあります。時間が来たらその問題はサクッと見捨てましょう。
まとめ
以上で記述模試では点が取れるのに共テでは点が取れない人に向けた、共テの点を伸ばす方法についての解説を終わります。
共テは記述式の試験と比べて特徴がはっきりしており、対策をするかしないかで大きく点が変わってくる試験です。是非この記事の内容を参考にして記述試験だけでなく共テの点もしっかりと伸ばしていってください!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
こちらもどうぞ
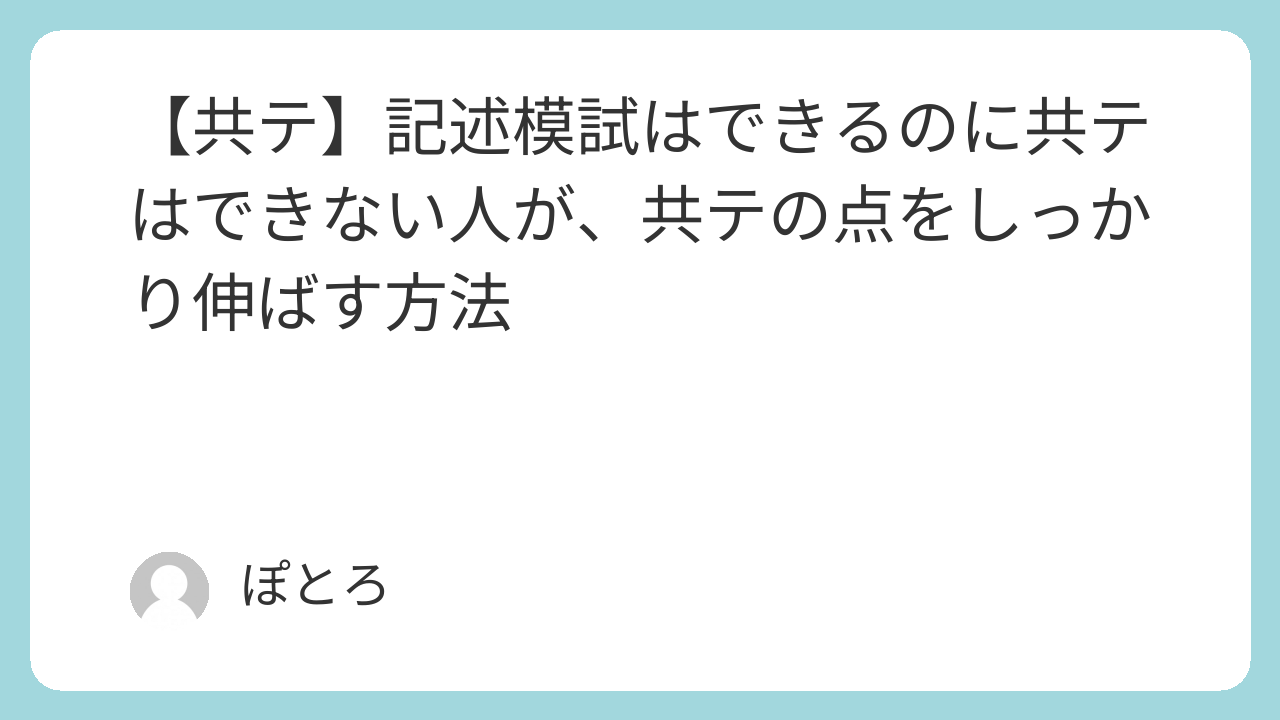
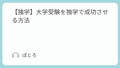
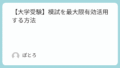
コメント