こんにちは!現役京大生のぽとろです!
今回は模試の活用方法について解説していきます!模試に関しては「どんな種類の模試を受けたらいいの?」、「どの時期に受けたらいいの?」、「判定が悪かったらどうしたらいい?」、「どのくらいの判定を取らなきゃいけないの?」などの質問をよく見かけます。私自身、かつて模試に関しては様々な悩みを抱えていました。
そんな悩みを抱えていらっしゃる方々に向けて、私が京都大学に合格するまでの経験から、模試の受け方、選び方、捉え方について解説していきます!興味のあるところだけでも読んでいただけたら嬉しいです。
どんな模試を受けるべきか
まずはどの模試を受けるべきかです。模試の種類としては「共テ模試」、「記述模試」、「冠模試(大学名を冠した模試)」の三つがあり、各予備校が開催しています。
受けるべき模試は志望校によって変わってきます。
大半の人は記述模試を受けると思います。これに加えて共テが必要なら共テ模試を受けるというのが一番スタンダードです。ただし、浪人生は共テ模試は秋~冬のみ受ける、冠模試がある大学を志望している受験生は記述模試の頻度を減らすなどの選択も、成績や勉強計画によってはありです。
予備校に関しては基本的に河合塾と駿台だけでOKです。注意として、駿台全国模試は難易度や受験者層が比較的高めです。また、冠模試をたくさん受けたい場合は他の予備校の冠模試を受けることもできます。ただし、問題や採点の再現度に関しては河合塾や駿台が上です。
勉強計画への組み込み方
模試を受けるならその時間やお金を他の勉強をしたり、他の参考書の購入に充てたほうがよいと考えている人も少なからずいますが、模試は定期的に受けたほうが良いです。
理由は模試を定期的に受けることで勉強の目的や目標がはっきりし、モチベーション維持や勉強のペース維持に役立つからです。
したがって模試は定期的に、できれば1~2か月に一度以上は受けるようにしましょう。
また、模試を受けるにあたって「どうせ今の実力じゃ第一志望E判定だよ……」と言って受けるのを後回しにする人がいますが、これはあまりよくありません。判定がどうであろうと現状の実力を明確に認識しなければ、適切な勉強計画は立てられません。科目ごとの偏差値や順位、大問ごとの点数などをしっかり分析して勉強計画に役立てることができれば成績は効率よく伸ばすことができます。ビビらずガンガン受けましょう!
模試の判定はどう捉えるべきか
次に模試の判定の受け止め方について解説します。よく予備校などで「模試の判定に一喜一憂するな!」ということが繰り返し言われていますが、具体的にどうしたらいいのかは意外と誰も教えてくれません。ここでは判定が良かった時と悪かった時の捉え方についてそれぞれ解説していきます。
ちなみにどこからが「良い判定」でどこからが「悪い判定」かは人によりますが、一般的には現役生はB以上、浪人生はA以上が取れると良いとされています。
まずは判定が良かった時です。まずは素直に喜びましょう。その判定に至るまで努力できた自分をほめてあげてください。
その後には、なぜ良い判定が出たかのかを考えましょう。具体的には「どの教科が良かったのか」、「その教科でなぜ良い点が取れたのか」です。
例えばあなたが模試に向けて必死で努力した英語のおかげで良い判定が出ていたならそれは素晴らしいことですが、仮にあまり勉強していないけどたまたま取れた数学で判定が良くなっていたとしたら、次回からは少し気を付けなければなりません。
というのも、「たまたま良い点が取れた」は案外起こりうる出来事だからです。「たまたまでも良い点が取れたのだからそれは喜べばいいじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、仮にあなたが入試本番までずっと「たまたま」良い点が取れてしまったら、自分の実力を過信してしまうことになります。そういう人がいわゆる「逆転不合格」をやってしまうわけです。成績が悪かった時はもちろんのこと、良かった時にもしっかり「なぜ良い成績が取れたのか」を確認するようにしましょう。そして「たまたま」だったと気づいたならば、次からはその点を取るのが必然になるように勉強していけばよいです。
次に判定が悪かった時です。当然なぜ点が悪かったのかを振り返る必要がありますが、この時やるべきことがふたつあります。
まず一つ目は、どの分野、どういうタイプの問題が解けなかったのかをしっかり見つめなおすことです。大問ごとの復習はやっている人は多いですが、そこからさらに細かい分析ができている人は少ないです。例えば英語で長文問題ができていなかったとしましょう。そこからさらに踏み込んで、できていなかったのは和訳問題なのか、文脈把握の問題なのか、語彙の問題なのかなどを明確にします。例えば和訳ができていなかった場合はさらに自分に足りなかったのは語彙なのか、文構造の把握なのか、文脈を理解することなのか、そしてさらに踏み込んで………と繰り返していきましょう。いずれピンポイントな答えが出るはずです。そこまでたどり着いたらようやく二つ目のステップに進むことができます。
二つ目にやるべきことは、上記のように自分のピンポイントな弱点をどのように克服するかを考えるということです。上記の方法でマクロな視点からミクロな視点へと分析が進んできたわけですが、そのマクロからミクロのグラデーションの中でどのポイントを復習の課題とするかということです。範囲が大きすぎると本当にやるべきことが不明瞭になってしまいますし、小さすぎるとそれが適用できる問題が非常に少なくなってしまいます。
復習の目標は「模試でできなかった問題と、それと同様の問題に次出会ったときに、模試と同じ間違いをせず、必ず正答できる」レベルを目指しましょう。細かすぎず、おおざっぱすぎないというのは初めはかなり難しいですが、この作業を繰り返していると自分の弱点やその克服のためにするべき勉強をだんだん明確に認識できるようになっていきます。
まとめ
以上で模試を最大限活用する方法についての解説を終わります。志望校合格には模試を効果的に用いることは必須といっても過言ではありません。是非この記事の内容を参考にして模試をうまく使えるようになってください!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
こちらもどうぞ
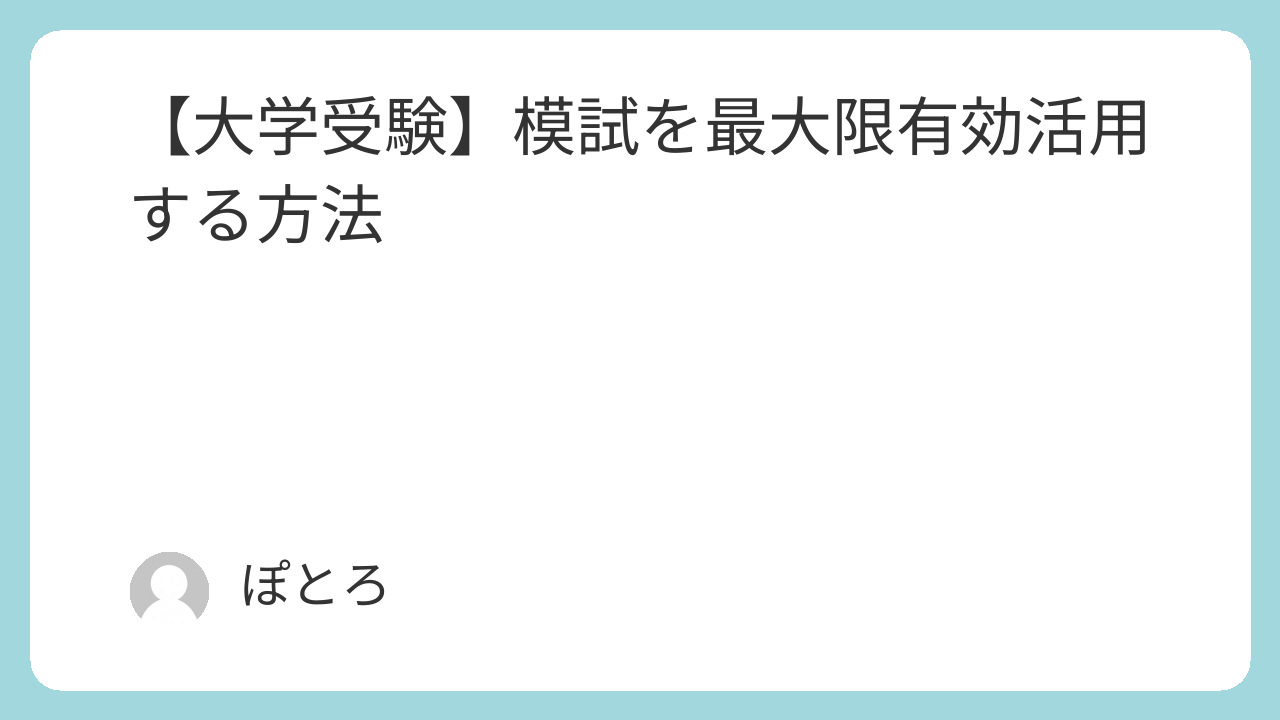

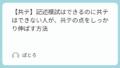
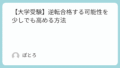
コメント