こんにちは!現役京大生のぽとろです!
今回は私が京都大学に合格した経験から、共通テスト地理で7割、8割、9割を取る方法をそれぞれ解説していきます。
必要な情報を手早く参照できるように、各参考書は【特徴】、【使い方】という二つの項目で解説しています。興味のある所だけでもご覧ください。
共テ地理という科目の性質
まず、共テ地理で点を稼ぐためには「理解」と「暗記」の両方が必要です。
巷では「共テ地理はちゃんと教科書を理解していれば解ける!暗記はいらない!」というアンチ暗記派閥や、「地理も所詮は社会科目なのだから暗記で十分だ!」という暗記大好き脳筋派閥が散見されますが、結論は理解も暗記も必要だと言えます。しかし、目標点や実力に応じて「暗記を重視するフェーズ」や「理解を重視するフェーズ」が存在することも事実です。
この記事で紹介されている参考書を取り組む中で、ぜひ「理解」と「暗記」を一方に偏ることなく学んでいってください。
共テ地理は、コツを掴めばある程度の点数は比較的簡単に取れる科目ですので、この記事を参考に最速で点数を伸ばしていってください!
それでは具体的な参考書や勉強法について解説していきます。
「70点」に到達する方法
必要な参考書は以下の4冊です。
- 共通テスト地理総合、地理探求の点数が面白いほど取れる本
- 資料集
- 地図帳
- 瀬川聡の共通テスト地理 超重要問題の解き方
共通テスト地理総合、地理探求の点数が面白いほど取れる本
【特徴】
いわゆる「黄色本」というやつですね。共テ地理対策を始めるにあたって最適な参考書です。初めて学ぶ概念が分かりやすい言葉で説明されており、初学者でも理解しやすいです。
【使い方】
この本はいわば教科書ですので、「地理という科目についてインプットする」と「他の参考書で問題を解いてわからないことがあったら立ち返って調べる」という二つの役割があります。
まず初めにインプットについてです。目安は2周です。1周目はざっくりした理解で全体像を把握することを目指します。後述の「資料集」と「地図帳」を適宜参照しながら読みましょう。理解度は50%ほどで十分です。
次に2周目は1周目で掴んだ全体像を手掛かりに、細かい知識をインプットしていきます。この時はある程度細部まで読み込みましょう。理解度は90%を目指してください。
2周目に100%にする必要はないのか?という疑問があるかもしれませんが、かなり細かい要素まで覚えようとすると逆に効率が悪くなってしまうので、現段階では90%を目指し、残りの10%は問題演習をする中で覚えていけばよいです。
地図帳(学校配布のものでも可)
【特徴】
世界各地の地図が様々な縮尺で掲載されています。
【使い方】
知らない地名(都市の名前、山の名前、川の名前など)が出てきたときに調べましょう。名前だけで情報を覚えるのは効率が悪いので、地図を見て画像として記憶しましょう。共通テストでは地名そのものを覚える必要はありませんが、ある程度この国のここに〇〇川がある、〇〇山脈があるなどの情報は必要です。新しく覚えた事柄を書き込んでいけば復習にも便利です。
資料集(学校配布のものでも可)
【特徴】
地形の写真や都市の風景、統計などが載っています。
【使い方】
地形や自然現象などが文章だけでは理解しにくい時に使います。参考書は文章でしか説明されていないことが多いので、イメージをしっかりつかむためにも資料集は必要です。
瀬川聡の超重要問題の解き方
【特徴】
共通テスト、センター試験の過去問の中から良問を厳選し、分野ごとに勉強できるようになっています。解説も細かくて良いです。
【使い方】
黄色本を2周した後に取りかかかります。この参考書では共テ地理において重要な「アタマの使い方」を学びましょう。共テ地理は先述の通り知識だけでは解けません。覚えた知識をどう使っていくかが重要です。この参考書の内容をきっちり理解し、共テ地理の思考法を習得できれば70点を切ることはまずなくなると言っていいでしょう。
80点に到達する方法
ここからは上記の参考書で身に着けた知識や思考法を、実際の問題をたくさん解いてさらに実戦的なものにしていきます。問題を解いていると必ず知らない知識が出てくるはずなので、その都度黄色本や超重要問題の解き方に戻って確認しましょう。
必要な参考書は以下の通りです。(すべて必要というわけではありません。自分に合うものを少なくとも一冊以上やってください。)
- 過去問
- 予想問題集
過去問
【特徴】過去に出題された問題を解くことができます。
【使い方】ひたすら知識や思考法のアップデートを目指します。「一度本番で出た問題はもう次は出ないから過去問はやっても意味がない」と言われることもありますが、全く同じ問題は出なくても似たような手順を踏んだり、近しい知識が必要だったりすることもあるので、ぜひとも過去問に取り組みましょう。
ただ、センター試験の問題は若干共通テストとは違う形式なので、知識の確認として使いましょう。
予想問題集
【特徴】
予備校が出している予想問題に取り組めます。基本的には分野ごとではなく1セット分(つまり60分測って解く形式)ずつです。難易度は河合塾<駿台です。他の予備校も予想問題を出していますが、基本的にはこの二つで十分です。
【使い方】過去問同様に知識と思考法のアップデートを目的に使いましょう。
過去問と予想問題集、どう使い分ける?
基本的に過去問は演習量を稼ぐために使います。予想問題は直前期に時間を測って解くために使います。ただし、河合塾の予想問題は若干易しめなので、演習量確保に使ってもいいかもしれません。
90点に到達する方法
基本は上記の過去問や予想問題をたくさん解くことが中心です。まずは問題演習の量をひたすら稼ぎましょう。そのうえで、追加で次の参考書も取り組めば知識不足で問題が解けないということはほぼなくなります。
統計・データの読み方が面白いほどわかる本
【特徴】
過去問をベースに様々な統計やデータが掲載されており、統計やデータのどこに注目すべきか、どこを暗記すべきかが解説されています。
【使い方】
最初は一通り読み、解けなかった問題を復習しつつ暗記すべき事項をひたすら暗記していきます。
共テ地理で90点以上取り続けるのは至難の業
共テ地理は一度ある程度の知識や思考法が身に着けば簡単に70点以上は取れるようになる科目ですが、その反面90点以上の高得点を継続して取るのは難しい科目でもあります。理由は問題を解くのに想定されている思考法を、すべての問題で思いつくことが難しいからです。出題者の想定通りに頭を動かし続けるのはほぼ不可能と言っていいでしょう。
ですから80点が安定したあとは「90点以上を安定させる」ことよりも、その時間を他の科目の勉強に割き、地理は「80台後半~90台前半を取り続ける」ことを目標としたほうが共通テスト全体では高得点を望めます。
まとめ
以上で参考書の紹介を終わります。冒頭で書いた通り、共テ地理には「理解」と「暗記」の両方が必要です。それを頭の片隅に置いておきつつ、ここで紹介した参考書を使って最速で目標点まで到達してください!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
こちらもどうぞ
【現役京大生が教える】数学の点数を爆上げさせた解法暗記の方法 | 多浪京大生による大学受験徹底考察ブログ
【共テ】記述模試はできるのに共テはできない人が、共テの点をしっかり伸ばす方法 | 多浪京大生による大学受験徹底考察ブログ
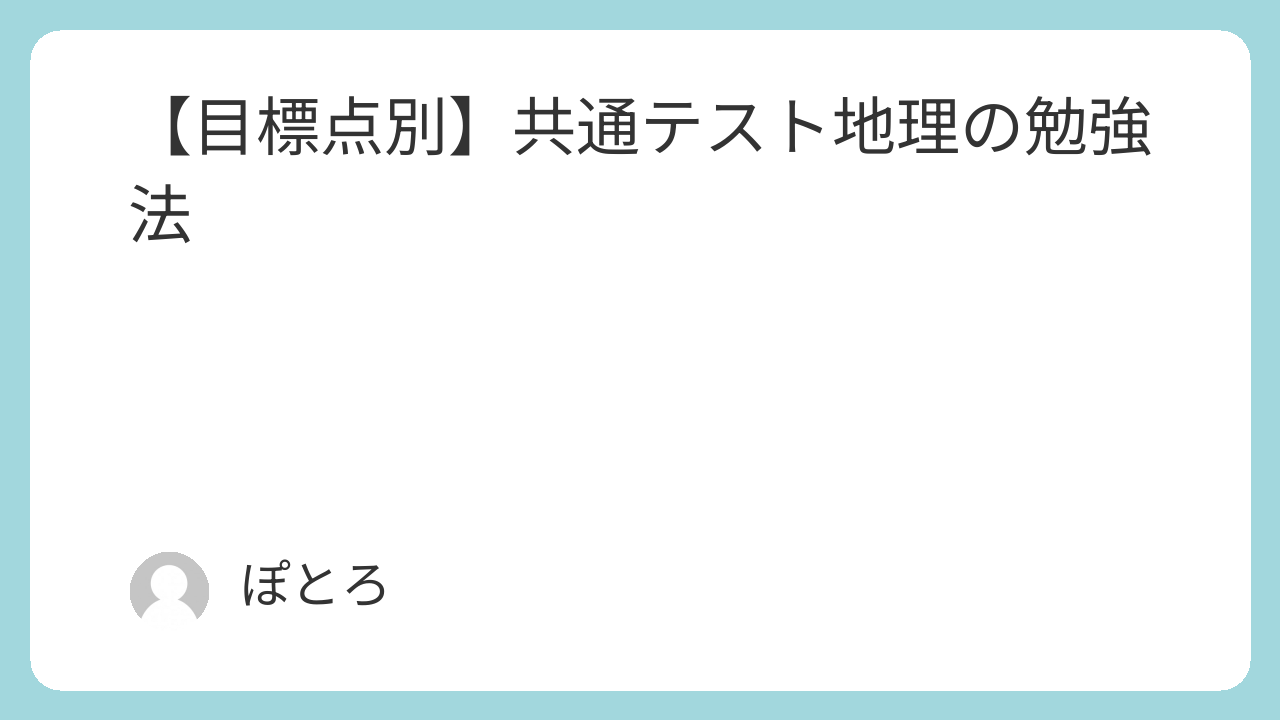
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fd7ec3.ca4feb82.49fd7ec4.0ba0bf16/?me_id=1213310&item_id=21297697&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2369%2F9784046062369_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fd7ec3.ca4feb82.49fd7ec4.0ba0bf16/?me_id=1213310&item_id=21415752&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7395%2F9784807167395_1_118.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fde427.47dc9946.49fde428.1ef78f82/?me_id=1259747&item_id=16152547&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2025%2F007%2F34713061.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fd7ec3.ca4feb82.49fd7ec4.0ba0bf16/?me_id=1213310&item_id=21637561&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4530%2F9784046064530_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fd7ec3.ca4feb82.49fd7ec4.0ba0bf16/?me_id=1213310&item_id=21637567&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4547%2F9784046064547_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a010afc.44d22ae6.4a010afd.939b95f1/?me_id=1285657&item_id=13028898&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01155%2Fbk4325267069.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fd7ec3.ca4feb82.49fd7ec4.0ba0bf16/?me_id=1213310&item_id=21611492&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9635%2F9784777229635_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49fd7ec3.ca4feb82.49fd7ec4.0ba0bf16/?me_id=1213310&item_id=21648709&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4962%2F9784796164962.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a00f033.ffcfe7b2.4a00f034.cd940e13/?me_id=1278256&item_id=21430169&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9432%2F2000011559432.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
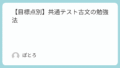
コメント