こんにちは!現役京大生のぽとろです!
今回は私が京都大学に合格するために大いに役立った「まとめノート」について、効率的な使い方を解説していきます!
受験生のみなさんのなかには「まとめノートってどうやって使えばいいんだろう?」、「まとめノートって本当に効果あるの?」、「復習のためにまとめノートを使ってみたい!」のように考えている方も多いでしょう。
私は多浪の末に京都大学に合格しました。長年の苦労の中で編み出した画期的な方法が「まとめノート」だったわけです。
この記事では私が京大合格のために使ったまとめノートの使い方について詳しく解説していきます!現役生・浪人生を問わず、ぜひ参考にしてください!
そもそもまとめノートって?
そもそもまとめノートを知らない人、よくわからな人に向けて、まとめノートとはどんなものなのか説明します。
まとめノートとは「参考書や問題集を使っているときに現れた新しい知識や解法を、一冊のノートにまとめておくもの」です(個人的な見解ですが、おそらく一般的にもこのような解釈だと思います)。
要するに後で復習しやすいように、そして一回見たものを忘れないようにまとめておこうというコンセプトですね。
巷では「まとめノートは意味ない」とか「まとめノートは時間の無駄だ」とか「まとめノートは自己満足にしかならない」といった言説を見かけますが、全くそんなことはありません。
むしろ正しい使い方をすれば非常に効率的に知識を整理し、復習をスムーズに行うことができます。
まとめノートの利点
上記の通り、まとめノートは覚えておくべき事柄をまとめていくものですから、それが無い場合と比較して非常に効率的に復習を行うことができます。
仮にまとめノートを作らなかった場合のことを考えてみましょう。ある参考書で覚えておくべき事柄が出てきた際、当然その参考書を何度か解いてその事柄を頭の中に定着させるよう努力すると思います。
しかし、その参考書を一通り終えてしまったらどうでしょう。もう二度とその事柄を復習する機会はないかもしれません。他の問題集で再び現れる可能性もありますが、ずっと入試本番まで現れない可能性も大いにあります。
受験生は参考書を何冊も解き、次々に新しい知識をインプットしていかなければいけませんから、些細な知識が数週間、数か月経って頭から抜けてしまうのは必然ともいえるでしょう。
これを解決できるのがまとめノートなのです。
一冊のノートにまとめておくことで、参考書を使い終わった後でも復習すべき内容に継続的に触れることができます。
また、問題を解いているときに以前使った知識を振り返りたいときにも効果的です(まとめノートがなければ毎回参考書を引っ張り出して探すことになってしまいます)。
合否を分けるのはたった一つの些細な知識です。
急がば回れではないですが、細かい部分にこだわって丁寧に知識や解法を蓄えていくことが合格率を上げることにつながります。
また、世間ではあまり意識されていませんが、まとめノートには実はもう一つの大きな利点があります。
それは自分だけのお守りが作れるということです。
まとめノートに覚えるべき知識や解法を常に書き続けていれば、そのノートは自分専用の参考書になるといっても過言ではありません。つまり、まとめノートさえ見ればそれまでのすべての問題の復習ができるようになるのです。
試験会場では「まとめノートさえ見ておけば大丈夫」と思えるようになり、お守り代わりになってくれるというわけです。
試験会場に何冊も問題集を持っていくのは重くて不便ですし、でも何も持って行かないとなんだか不安ですよね。まとめノートがあれば試験前にさっと見るだけでリラックスした状態で試験を受けることができます。
実際私は試験会場にはまとめノートしかもっていきませんでしたが、まったく不便や不安を感じることはありませんでした。むしろ何冊も参考書を持ってきている受験生を見て「効率が悪いなあ」とすら思っていました(笑)
まとめノートの作り方
科目の数だけ大学ノートを用意
私は科目数分の大学ノートを用意し、それぞれを一教科分のまとめノートとしていました。
また、国語は「現代文」と「古文」の二冊を、英語は「読解」と「英作文」に分けていました。さらに英単語も別で作り、その中で「読解用(英単語の和訳を覚える)」と「英作文用(日本語の表現に該当する英語の表現を覚える)」というように分別してノートを作っていました。
これらは同じ「国語」や「英語」であっても現代文と古文、読解と英作文はそもそも頭の使い方が違う分野ですので、分けることを推奨します。
また単語の暗記も、解法や知識の暗記とは異なる頭の使い方をするものですから別のほうがいいでしょう。ちなみに古文単語も分けてましたが、別で一冊作るほどの量にはならないと思ったので一冊のノートを前と後ろに分け、前を文法や解法などの知識系、後ろを古文単語というように分けてまとめていました。
たまに一冊のノートに全教科分のまとめを書くという人もいますが、量が増えると結局ノートを増やす羽目になりますし、教科ごとの復習ができないので個人的にはナシです(コンパクトなのはいいですが、各教科作っても高々数冊ですからね)。
書き方
次に書き方についてです。
巷では「ノートの一ページを半分にして左になんとかを書いて右に……」のように細かいことをやってる人もいますが、私はこんなことは面倒でできませんでした(笑)
私がやっていたのは単純明快、復習すべき内容がでてきたらノートにひたすら箇条書きで書いていきます。
これが一番楽ですし、特にこれで困ったこともないです。
まとめノートを使う上で一番大切なのは「知識のデータベース」を作ることです。面倒くさくてやめてしまったり、些細な内容だからと書かなくなってしまったりしては元も子もありませんから、ただひたすら書き連ねればいいのです。
ちなみに書き連ねるときは「余白を確保しておく」とよいです。
色んなことを書いていくと以前の知識にプラスで付け加えたくなることも出てきます。その際に余白が無いと困ってしまいますので、多少余裕をもってゆったりと書いていくと後々便利です。
まとめノートに書くべきこと
ここまで方法論を解説してきましたが、ここでは具体的にどんなことを書くべきかを解説します。
基本的には問題集を解く中で間違えてしまった問題を、次は間違えずに解けるようにするためにエッセンスを抽出してまとめノートに書きます。
この時、具体的すぎても抽象的すぎても効果が薄れてしまいます。
例えば数学の問題で間違えた時、その問題の数字や式をそのまま写してもあまり意味がありません。逆に広すぎてもダメです(例えば「計算を丁寧にやる」など)。
私はまとめノートに記入する際、「その文言を見れば元の問題が確実に解けるようになる」ということを基準としていました。
したがって間違えた時に、「自分に足りなかったものは何か」を深堀り、間違えた原因をシンプルに言い表す必要があります(原因は一つだとは限りません。複数の原因があれば複数の項目をまとめノートに記述してください)。
最初は面倒に感じるかもしれませんが、このような「言語化」を繰り返しているうちに、自分の弱点や不足していることを明確に意識できるようになり、効率よく勉強を進められるようになります。
また「言語化」を何度もしているうちに問題の本質が掴めるようになってくると、汎用的な解法を身に付けたり、体系的に解法を整理したりできるようにもなります。
実際私は、特に数学においてまとめノートのおかげで解法を体系的に習得することができたと感じています。まとめノートを作る前は解法は「思いつくもの」でしたが、まとめノートを作り始めてから解法は「整理されている知識の中から選び出すもの」になりました。結果的に数学の点はかなり安定するようになりました。
慣れないうちは難しいと感じるかもしれませんが、継続しているうちにコツがつかめてくるはずです。まずは始めてみましょう、そして続けてみましょう。
ちなみに、どのくらい抽象的に、もしくは具体的に書けばよいか迷った場合は一旦抽象的なことを書き、その下に具体例を追加するという方法でもよいです。ものによってはこっちのほうが復習がスムーズなこともあります。迷うぐらいならちょっと多めに書いちゃっても大丈夫です。後で呼ぶんだと思ったら消せばいいですしね。とにかく楽な方法で継続することが大事です。
復習方法
復習は頻繁に行いましょう。
学校や予備校に行く電車の中、休憩時間、寝る前など隙間時間でさらっと見ればよいです。私はご飯を食べながらよく眺めていました。また、模試前には「まとめノートに書いてあることは全部答えられるようにするぞ」と意気込んで、もう一度しっかり見直すようにしていました。
何か紙に書いたりするわけでもないですし新しいことを学ぶわけではないので、それほど労力のかかることでもないです。
多くの受験生は復習をサボりがちですから、継続的にまとめノートを見直して復習し、差をつけましょう。
まとめ
まとめノートは私が京都大学に合格するうえで非常に役立ちました。まとめノートが無ければ合格していなかったといっても過言ではないでしょう。
受験生の方は是非この記事を参考にしてまとめノートを使いこなし、復習で他の受験生に差をつけていっていただければと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
こちらもどうぞ
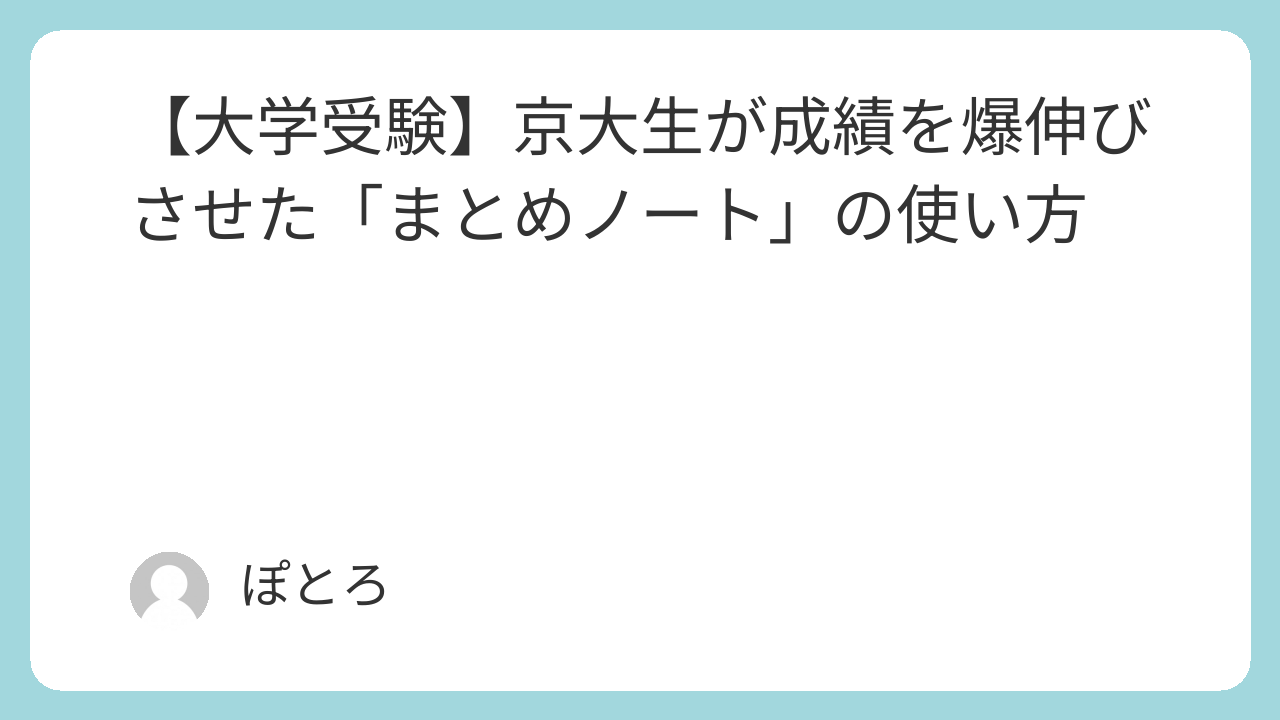
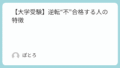

コメント