こんにちは!現役京大生のぽとろです!
今回は私が京大合格のために活用した、数学の「解法暗記」について解説していきます!数学を得点源にしたい人、数学の点数を安定させたい人必見です!
皆さんは数学で安定して高得点を取れているでしょうか。私は多浪の末に京都大学に合格したのですが、何年も数学の点数には悩まされ続けました。
この記事では当時の私のような悩みを持っている受験生の皆さんに、私が多浪の中で編み出した解法暗記の方法について解説していきます。
興味のあるところだけでもご覧いただければ幸いです。
私の経験談
まずは私の経験について書きます。
私は多浪をしているので複数回受験に失敗しているわけですが、何を隠そう、不合格の理由はほぼ数学での失敗でした。多くの時間を数学の勉強に割き、模試では合格に必要な点が取れていたのですが、なぜか本番ではことごとく失敗しました。
当時は解法暗記を軽視していたため、再現性の無い勉強しかできていなかったのです。そこで勉強法を見直すことにしたのですが、その時重点的に行ったのが解法暗記でした(実際に行った勉強内容については後述します)。
その結果、それまで不安定だった数学の点数がかなり高水準で安定し、本番でも想定通りの点数を取ることができ、無事京都大学に合格することができました。
解法暗記が私を京大合格に導いてくれたと言っても過言ではありません。
なぜ解法暗記が点数の安定・上昇に効果的なのか?
ここからは解法暗記が点数を安定・上昇させてくれる理由について解説していきます。
解法暗記の一般的な認識
そもそも世間で解法暗記はどのように考えられているでしょうか。一般的に解法暗記は「網羅的な問題集(青チャートやフォーカスゴールドなど)の基本的な解法を覚えること」だとされていると思います。
この認識には「応用・発展レベルの問題は、基本的な解法を組み合わせ、思考力を使って解くものだ」という意図が暗に組み込まれています。
皆さんの中にもこのような考え方をしている方は多いでしょう。私も以前はそうでした。
このような考え方は、数学の才能がある程度備わっている人、基礎的な内容のみ解ければ合格可能な大学を志望している人には効果的です。
しかし、もしあなたがそうでない(特に、現在数学の点数が安定していない)場合、考えを改め、後述する解法暗記の方法にシフトするべきです。以下で順に理由を説明します。
実際に行うべき解法暗記
実際に行うべき解法暗記は「基礎のみならず応用・発展レベルの問題の解法も全て暗記し、可能な限り思考力を使うシーンを減らす」というやり方です。
応用・発展レベルの問題もひたすら暗記に頼るというところがミソです。
「そんな方法で本当に応用・発展レベルの問題が解けるのか」、「そんなやり方で合格水準の点が取れるのか」、「思考力は必要ではないのか」などの反論があると思いますが、それぞれ詳しく解説していきます。
解法暗記を行うべき理由
解法暗記を行うことで得られるメリットには以下のようなものがあります。
・典型問題で確実に正答できるようになる
・再現性が向上する
・緊張していても普段のパフォーマンスが出せるようになる
・難問や奇問から素早く撤退できる
順に解説していきます。
典型問題だけで合格できる!
まず大前提として皆さんに覚えておいてほしいことがあります。それは「入試数学では典型問題さえ解ければ受かる」ということです(ここでいう典型問題は有名な参考書(難易度の高いものも含む)に解法が乗っている問題を指します)。
思考力や発想力が問われるといわれている京大の入試問題でさえも実はそうなのです。どの大学も過去にどこかで出題された問題の使いまわししかしていないのです。
時々目新しい問題が出ることもありますが、それも「いくつかの定番の解法を組み合わせただけ」のことが多いです。たまに本当に見たこともない解法でしか解けない問題もありますが、そういう問題はどうせほかの受験生も解けません(一部の天才は解いてきますが無視でいいです。天才でなくても合格できる方法はちゃんとありますから)。
合否を左右するのは典型的な解法を覚えていたかどうかです。ひらめきや発想が優れているかどうかではありません。
それでは、典型的な問題はどうしたら解けるようになるのでしょうか?賢い方はもうお気づきでしょう。そうです、解法暗記です!
普段の勉強や模試の中で、知らない解法を見たらどんな難問だろうと全部覚える。これさえできていれば、数学で不利になることはまずなくなります。
思考力などという幻想は捨てましょう。やるべきは地道に解法を蓄え続けることだけです。
解法暗記のメリット
入試数学に必要なのは典型問題の解法暗記であるということは理解していただけたでしょうか。
ここではそれ以外の解法暗記のいくつかの大きなメリットについて解説します。まずは「再現性が大幅に向上する」ことについてです。
多くの解法を暗記していれば「〇〇の形を見たときに試すべき解法はAとBとCだけ」のように機械的に問題を解くことができます。これによって試験問題の傾向に左右されない、確かな再現性が得られます。
ちなみに私が数学のせいで不合格になってしまった原因は、本番で傾向の変化が起きたことにもあります。解法を覚えることをおろそかにし、なんとなくその場の思い付きで問題を解いていた私は、突然いつもと違う傾向の問題が出題され頭が全く動かなくなってしまいました。
しかし、解法暗記を徹底して行った年は本番で例年あまり出ていないような問題が出てもしっかりと対応し、得点を稼ぐことができました。
入試で急にそれまでとは違う傾向の問題が出てきたとしても、再現性があれば大きく点数を落とすことはありません。
また、先ほど「機械的に解く」と書きましたが、これには副次的な効果もあります。
それは「本番で緊張していても普段通りのパフォーマンスが発揮できる」ということです。
「本番緊張して解けなかったらどうしよう」というのはよくある悩みですが、解法暗記はこれも解決してくれます。
理由は解法暗記は思考力に頼らないからです。「緊張で解けなくなる」は正確に言えば「緊張で頭が動かなくなり、思考が鈍る」ということです。
思考に頼らなければ緊張で多少思考が鈍ったとしても手の動くスピードに影響はありません。ただ、覚えているものを出力するだけでよいのです。
また、これもさらに副次的な効果ですが、「難問・奇問から素早く撤退できる」というメリットもあります。
入試問題では「ほとんど誰も解けない問題」がたまに出題されます。このような問題は一刻も早く撤退すべきです。
解法暗記がしっかりできていれば「自分の知っている解法が通用しないならきっとほかの人も解けていないだろう」と素早く判断することができます。
実際の解法暗記のやり方
解法暗記の必要性、重要性について理解していただけたでしょうか。
それでは具体的にどのような勉強法をすべきかについて解説していきます。
まずは当然網羅系参考書(青チャート、フォーカスゴールドなど)を確実にマスターしましょう。
その後は様々な応用・発展レベルの参考書を解くことになると思います。まずは自分のレベルに合った参考書を選んでください。そして最初はしっかり頭を使って解きましょう。後で暗記すればいいやと思って適当に解いてしまうと自分がどこまで理解しているか・していないかがわからなくなってしまい非効率です。
解いた後はしっかり解答解説を読み、その問題に正解できたかどうかにかかわらず知らない解法が出てきたらすべて暗記してください。
暗記の際に気を付けることが2つあります。「どういう場面でその解法を使うのか」、「なぜその解法を使うのか」を意識するということです。
漫然と解法を覚えても実用性は少ないです。前述のような「○○の形にはAかBかC」のように体系的に、機械的に解けるようになることが目標です。
まずはどういう状況で使う解法かをインプットしていきましょう。その解法を使う理由までわかっていれば解法の選択(上の例でいうとA、B、Cのどれを使うかという選択)も素早く行えます。
また、「こんな変な解法を使うことはないのではないか」というような解法に出会うこともあるかもしれません。
いちいち覚えるのは面倒なのでパスしたくなりますが、頑張って覚えましょう。そういう「変な解法」が本番に出題される可能性はありますし、その問題が合否を分ける可能性もあります。
本番で見たことのある問題が解けなかったら元も子もありません。急がば回れではないですが、解法暗記をすると決めたなら覚悟を決めて地道に、一つずつ覚えていくしかありません。
まとめ
解法暗記は入試数学の点を確実に上げ、そして安定させるには必須です。
思考力に頼っていいのは一部の才能のある人たちだけです。大量に暗記することはとても大変なことですが、地道に積み上げていけば本番も必ずうまくいきます。
私のように数学で失敗する受験生が少しでも減り、皆さんの数学の点が少しでも上がることを願っています。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
こちらもどうぞ
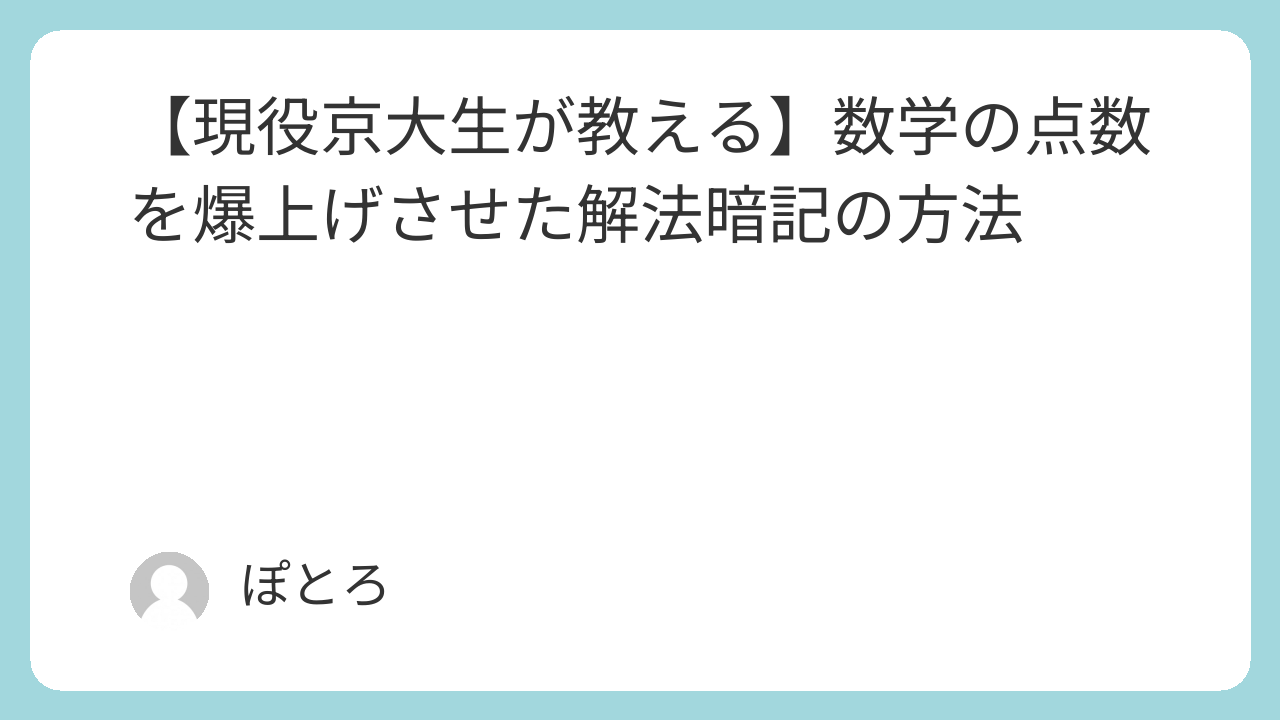

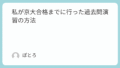
コメント