こんにちは!現役京大生のぽとろです!
今回は大学受験の独学の仕方について解説していきます!
私はいわゆる自称進学校出身で学校は頼れる存在ではなく、予備校も金銭的に行ける状況ではありませんでした。しかし周りの助けが無い中で様々な方法を試して少しずつ成績を伸ばし、最終的には独学で京都大学に合格することができました。
その経験を現在独学で学力を伸ばそうとしている高校生や浪人生の皆さん、そして独学を始めようとしている熱心な方々に伝えたいと思いこの記事を書きました。また、大学受験以外の資格勉強などにも応用できる内容となっています。
ぜひ興味のある項目だけでも参考にしていただければと思います。
独学のメリット
まずは独学のメリットについてです。最も大きなメリットは「自分のペースで勉強を進められる」ということです。
例えば高校に通っていると授業や課題などで自分のペースというものはあまり確保することができません。このような状態では自分にとって進度が遅すぎたり、逆に早すぎたりすることもよくあります。そもそも集団教育はそのような問題を逃れられないのです。
集団から離れて独力で進めていくことができれば効率は最も高水準になります。また、予備校に行かなくて済めば金銭的な支出が抑えられる、拘束されずに自分の好きな時間や好きな環境で勉強できる、自分に適した参考書を使うことができるなどのメリットもあります。
独学のデメリット
独学の仕方を考えるうえではデメリットは明確に意識しておく必要があります。デメリットは大きく分けて「情報が不足しがちになる」、「勉強を習慣化しにくい」、「相談できる人がいない」の3つです。
「情報が不足しがちになる」については、集団に属していれば得られる様々な情報を入手することができないという状態です。例えば高校であれば「〇月には△△の勉強をするのが良い」、「そろそろ出願の準備の時期だ」、「●●という参考書はためになる」のような情報が友達や先生から得られます。自分一人だけで考えるという状況では、思考や情報が偏りがちになってしまいます。
「勉強を習慣化しにくい」については、同じような目標を持ち、お互いに刺激を受けモチベーションを持続させられるというような人間関係を得にくいということです。人の目があると「自分もやらなきゃ」という気持ちになり自然と継続的に勉強を続けていくことができますが、独学ではそうはいきません。これは短期的には分かりにくいですが、長期になるとはっきり表れる傾向です。
「相談できる人がいない」については、問題の解き方がわからないということ以外にも勉強法や事務的な手続き、精神的な面でのアドバイスを貰える人がいないという状況を指します。
これら3つのデメリットを乗り越えることが独学を成功させるうえで最も重要です。その乗り越え方について説明していきます。
独学を成功させる具体的な方法
以下の二つが独学成功の秘訣です。
・勉強計画の作り方、成績の伸ばし方を知る
・仲間を見つける
勉強計画の作り方、成績の伸ばし方を知る
もしかしたらこの記事を読んでいる方の中には「独学は全部自分で考える」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。実際に自分で考えるべき要素はたくさんあります。しかし「全部」である必要は決してありません。
いまやスマホで「大学受験 英語 勉強法」などと調べればいくらでも情報が集められる時代です。もちろんすべての情報を鵜吞みにしてはいけませんが、すべて自分で考えてネガティブな意味の「自己流」となるくらいなら人のやり方をまねてみるほうが効率がいいことも多いです。ぜひ今後のプランを決めるときは一度ネットで探してみましょう。
とは言ったもののこのページにたどり着いている方はそもそもネットで調べる習慣がある方も多いかもしれません。「ネットで調べるだなんて何をいまさら当たり前のことを」と思っていらっしゃるかもしれません。そんな方々に是非ひとつ覚えておいてほしいことがあります。それは「生存者バイアス」というものです。
生存者バイアス(せいぞんしゃバイアス、英語: survivorship bias、survival bias)または生存バイアス(せいぞんバイアス)とは、何らかの選択過程を通過した人・物・事のみを基準として判断を行い、その結果には該当しない人・物・事が見えなくなることである。選択バイアスの一種である。
生存者バイアスの例として、ある事故の生存者の話を聞いて、「その事故はそれほど危険ではなかった」と判断するという事例がある。それは、話を聞く相手が全て「生き残った人」だからである。たとえ事故による死者数を知っていたとしても、当然死んだ人達の話を聞く方法はなく、それがバイアスにつながる。
Wikipediaより
受験勉強に関する記事にも同じことが言えます。つまり、合格した人は「自分はこのやり方で合格できたのだからこのやり方は正しいはずだ」と思っていることもあるということです。実際は個々人の能力や育ってきた環境、適正などによって、同じ参考書でも使う人によって成績の伸び方は変わってくることは往々にしてあります。
独学をしているみなさんは、ネットで情報を集める上で「これは合格者のバイアスがかかった記事かもしれない」ということを念頭に置いて、個人的な意見に惑わされずに勉強法や参考書選びに取り組んでいただきたいです。
仲間を見つける
「独学だと言っているのに仲間とはどういうことか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが本来独学とは先生、教師などの勉強を教えてくれる人がいない情報を指すのであって友達を作ることは関係ないはずです。
屁理屈を言いましたが、仲間がいる効果は絶大です。お互いに学習状況を報告しあえば勉強習慣の維持にもつながりますし、勉強法や参考書選びなどの情報も交換することができます。また、悩みや困っていることを相談できる相手がいればよくない自己流に陥ることも防げますし、精神的にも支えになります。
偏った考えに陥ることは受験勉強において悪影響だということはイメージしやすいかもしれませんが、それに加えて「そのような状況に陥っているときは自分が偏った思考をしていることに気づかない」という側面もあります。私は何人も独学で勉強をしている人を見てきましたが、ほとんどの人が「自分のやりかたは正しいはずだ、自分は偏った考えはしていない」と思っているようでした。この点には十分注意が必要なのです。
作り方に関してですが、一番いいのは現実で仲間を作ることですが、それが難しければSNSでも構いません。スタディープラスやTwitter(X)があれば比較的簡単に仲間を見つけることができます。
まとめ
以上で独学を成功させる方法についての解説を終わります。独学はデメリットもありますがそれさえ克服できれば大きなメリットが得られます。是非この記事の内容を参考にして成績の伸ばしていただければと思います!
ここまで読んでいただきありがとうございました。
こちらもどうぞ
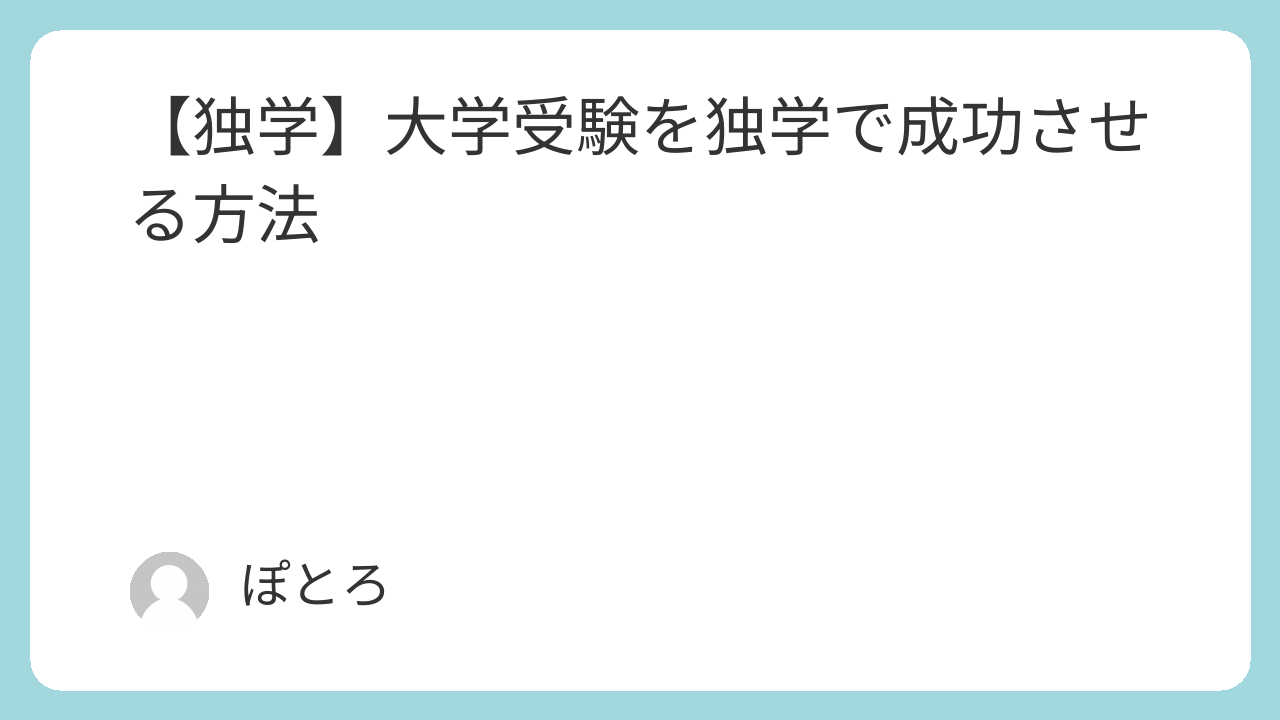
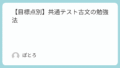
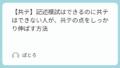
コメント